こんにちは!
今回はコスパ・タイパよく学べるドリルをご紹介したいと思います。
ただし現在わが子は長男が小4のため、今後の学力に寄与していくかは未知数。ただ、小学校のカラーテストはほぼ100点満点を取ってきます。
母の学習への考え方
私が基本としている考え方は、基礎を中心とした学習です。基本的に基礎固めをしなければ、応用問題を解いて落とし込むことは出来ないと思っています。
そして何と言っても勉強は継続することが大切。難問ばかり解くことは、小学生男子にとって負荷が大きすぎます。
朝学習のススメ
小学校で何時間も勉強してきた後に、宿題を終わらせ、さあ!ドリルをしようか!とならないのも分かっています。
そのため、わが家では、朝学習を行っています。
朝ごはんの後に、少しだけ勉強する習慣をつけるだけで、時間が捻出できます。
わが家では、朝学習を【あさべん】と呼んでいます。
おすすめドリルをご紹介
早速おすすめのドリルを紹介していきましょう。主に、朝学習で使っているドリルです。
早ね早おき朝5分ドリル 国語 文章読解

このドリルは学年ごとに分けられた国語の文章読解のドリルです。タイトル通り、朝の短い時間で取り組むことが出来る内容になっています。
長男は、本は読んでもらう派で、自分からはまったく読書をしません。そんな長男でも、このドリルの1節はスムーズに読み進め、数問の問題を解いていくことができます。
小学校のベテラン先生も、文章問題の練習として、プリント学習でこちらを利用されていました。
短い時間で完結できる、国語の文章読解ドリルを探している方におすすめです。
陰山メソッド 徹底反復 〇年生の漢字
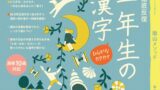
小学校で習う漢字の数は、合計で1026字だそうです。なんとなくで終わらせていると、最悪の場合は教科書の物語を読むことができない、なんてこともあります。
私は小学校の宿題でさぼりがちな音読を、欠かさず行うことが、とても大切だと思っています。なぜなら、習った漢字がすぐに物語に出てきて、授業でも家でも何度も目にすることで、自然に覚えて、記憶に定着していくからです。
話が少しそれましたが、このドリルは学年ごとに分けられた漢字を、教科書と異なる順番で勉強していくドリルです。
そんなことをしても忘れるのでは?と思うと思いますが、人の記憶は何度も思い出すことでより定着していくそうです。つまり、別のタイミングで学習することには、とても意味があります。
このドリルは、音読→漢字練習→短文の読み書き→熟語の練習→熟語のテストという構成で学んでいくもので、短期間で効果が出る仕組みになっています。
漢字と同時に熟語や使い方を知り、語彙力を増やせるドリルを探している方におすすめです。
毎日のドリル 小学1年 たしざん、ひきざん


このドリルは小学1年のたしざん、小学1年のひきざんが、別々にまとめられたドリルです。
長年愛用されているだけあって、勉強に不慣れな1年生でも取り組みやすく、すっと取り組むことができる内容になっています。
長男は、このようなドリルに取り組まず、公文式の算数に入会しましたが、次男は公文式は大変そうだと気付いているので、ひとまずこのドリルを繰り返し行っています。
少しずつ計算が速くなってきて、1日1枚だったところを何枚も取り組む姿を見て、胸が熱くなっています。
計算の基礎中の基礎の特訓をしたい方におすすめです。
科学のお話ドリル



このドリルは、長男がハマったドリル。小1〜小3まで種類があり、なぜ?どうして?と疑問に思うことを深掘りできる面白い内容です。
このドリルに出会って、子どもの興味のあるジャンルを勉強に組み込むことは、子どもの可能性を広げるためには必須なんだと思いました。イチオシです!
子どもの興味のあるジャンルで可能性を広げたい方におすすめです!夏休み等のまとまった時間を使ってやってみると良いと思います。
これから試したいドリル
この夏に学童保育で取り組む予定のドリルもご紹介します。まだ試していませんが、小4男子が食いつきそうなドリルなので楽しみです。
未知生物事件ファイル 小学4~6年

未知の生物のミステリーを文章読解にしたドリルです。少し情報が古いのでは?という口コミを見ましたが、小学生男子にとってそこは重要ではないような気がします。
この夏取り組んでみて、また記事にしたいと思います!
ドリルを家庭学習に取り入れるポイント
いくつかのドリルをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
お子さまの年齢や性格、好みは様々なので、本屋で一緒に選ぼう等と考えている方もいると思います。ですが、基本的に子どもは、こんなドリルやらへん!等と突っぱねてきます。
ママが情報収集して選んだ基礎のドリルを、まずはやってみる。これで十分だと思います。
ちなみにわが家では、ドリルを1冊終えたら、ハーゲンダッツのクリスピーサンドを買ってあげる!と言って、プチご褒美制度を導入しています。勉強の成果を実感するのは先でも、プチご褒美があるなら頑張れるのが小学生かな?と思っています。
ご家庭にあった勉強法やドリル、プチご褒美も実践してみてください。
私の楽天ROOMに、学年別のドリルをまとめています。ぜひご活用ください。

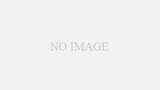
コメント